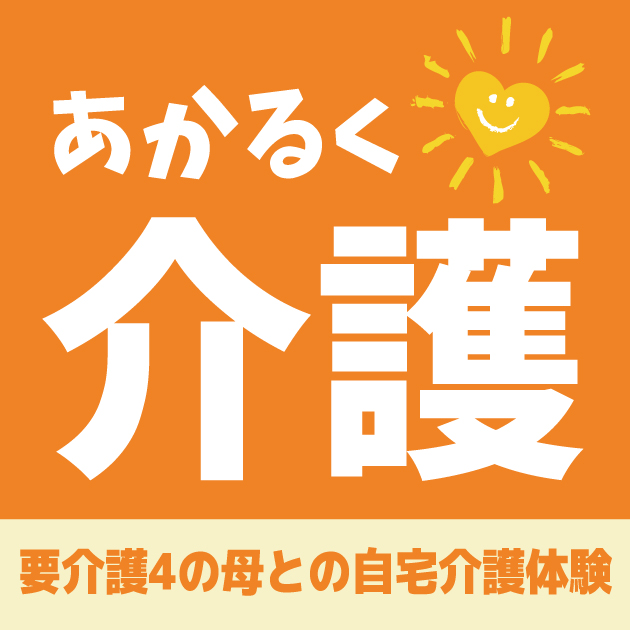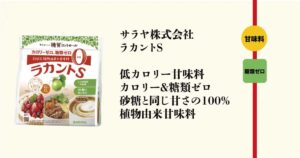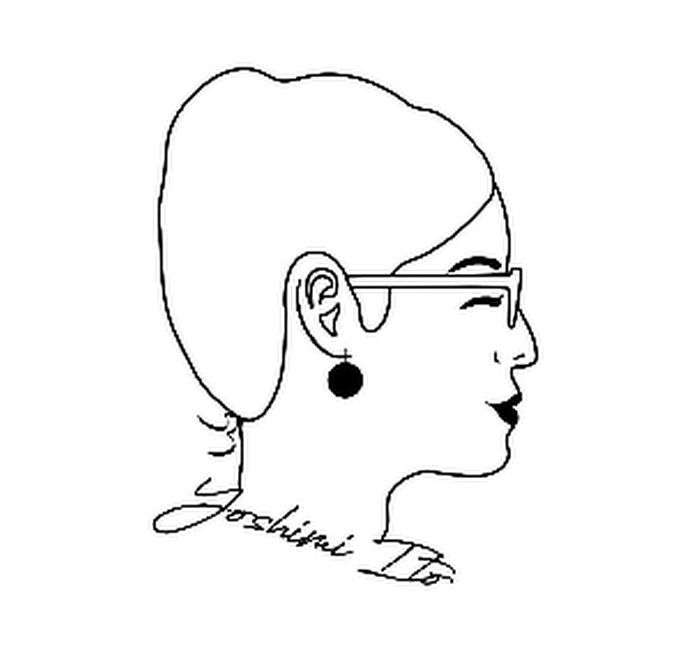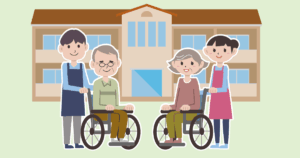はじめに|「制度改正」と聞いて、難しそう…と感じたあなたへ
「介護保険制度が改正されました」
ニュースや役所のお知らせで、そんな言葉を見かけても
「まだ先の話かな」
「正直よく分からない」
そう感じてしまう方は多いと思います。
私もそうでした。
でも、在宅介護を続けていく中で気づいたのは、制度の変化は、確実に“日々の暮らし”に影響してくるということ。
2024年4月に行われた介護保険制度改正は、「より安心して介護を受けられる社会」を目指した見直しです。
この記事では、在宅介護をしている立場から知っておきたいポイントだけを、やさしく整理してお伝えします。
1|介護保険料が少し上がりました
今回の改正で、65歳以上の方が支払う介護保険料は、全国平均で 月額6,225円 となりました。
前回より、約200円の増加です。
これは、
- 高齢者人口の増加
- 介護サービスを必要とする人が増えていること
- 介護職員の処遇改善(賃金アップ)
こうした背景によるものです。
金額は市区町村ごとに異なるため、
お住まいの自治体の案内を一度確認しておくと安心です。
2|「地域で支える介護」がさらに進みます
今回の改正で特に大きなテーマが、地域包括ケアシステムの強化です。
これは、
高齢になっても、できるだけ住み慣れた地域で暮らし続けられるように
医療・介護・生活支援を一体で支える仕組み
という考え方です。
具体的には、
- 医療と介護の連携強化
- 認知症ケアや看取りへの対応
- 災害時の支援体制づくり
などが進められています。
「体調を崩しても、遠くの施設に行かず、地域の中で支えてもらえる」
そんな介護の形が、より現実的になってきています。
3|介護の質を高める「LIFE(ライフ)」の活用
今回の改正では、介護の質を“見える化”する仕組みも重視されています。
それが「LIFE(ライフ)」と呼ばれる制度です。
介護サービスの内容や結果をデータとして蓄積し、より良いケアにつなげていく仕組みで、
- 本人の状態に合ったケア
- 無理のないサービス提供
を目指しています。
4|介護現場では「働きやすさ」も重視されています
介護を支えるのは、現場で働く人たちです。
今回の改正では、
- 介護職員の賃金改善
- タブレットやICT機器の活用
- 介護ロボットの導入
など、働き続けやすい環境づくりが進められています。
記録や見守りの負担が軽くなることで、職員さんが利用者一人ひとりと向き合う時間を確保しやすくなることが期待されています。
5|制度を「長く続ける」ための見直しも
日本全体で高齢化が進む中、
介護保険制度を どう持続させていくか も大きな課題です。
今回の改正では、
- サービス報酬の見直し
- 同一建物で複数利用者に訪問する場合の報酬調整
など、公平で無理のない運営を目指した調整も行われています。
6|今後、議論される可能性のあるポイント
今回の改正では見送られましたが、
今後、再び検討される可能性がある内容もあります。
- 自己負担割合の引き上げ(1〜3割 → さらに増える可能性)
- 要介護1〜2のサービスを総合事業へ移す案
- ケアプラン有料化の案
いずれも、利用者への影響が大きいため、慎重に議論が進められています。
おわりに|制度を知ることは、自分と家族を守ること
今回の介護保険制度改正は、「誰もが安心して年を重ねられる社会」を目指す一歩です。
保険料の負担は増えましたが、その分、介護の質や支援体制を守るための工夫が重ねられています。
誰もが、いつか「支える側」にも「支えられる側」にもなります。
だからこそ、制度を少し知っておくだけで、不安はぐっと小さくなります。
制度が変わるたびに「結局、私は何から始めればいいの?」と不安になる方も多いと思います。
制度の話は難しく感じますが、
実際の介護は「一つずつ」で大丈夫です。
在宅介護を始めるときの流れや、最初に知っておきたいことをまとめた記事があります。
▶ 「自宅で介護したい」と思ったら最初に読むページ|手続き・サービス・心構え
心構えたい方は、こちらの記事も参考にしてみてください。
制度の詳細や最新情報参考サイト
参考:・令和6年度 介護報酬改定について(厚生労働省)